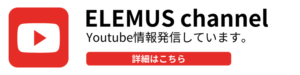日常生活において、環境への負荷を増やす問題の一つとして、商品を過度にキレイにみせて手に取らせる包装や、過度に新鮮さを強調した包装(いわゆる過剰包装)を小売店などで目にするようになりました。
商品を手に取るたびに、その包装に無駄な素材や資源が使われていることに、気づくことがありませんか?
この記事では、『過剰包装』に焦点を当て、製品のライフサイクルを通じて考え、日本の現状や、世界の動向について探っていきます。
「過剰包装」問題に取り組むための『ライフサイクルアセスメント(LCA)』の意義とは?
「ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment)」は、製品やサービスの一生を通じて環境への影響を評価する方法です。
製品の一生を通じて、資源やエネルギーの使用量や排出物量を定量的に理解することができます。
この評価により、環境への影響や資源・エネルギーの消耗を客観的に把握し、「過剰包装」問題などに対処する手段を見つけることができるのです。
製品の一生の【原材料調達 ⇒ 製造 ⇒ 流通 ⇒ 使用 ⇒ 廃棄】
における、どの段階で、環境負荷が発生しているか認識することで、効果的に環境問題に対する取り組みが可能となります。
また、「ライフサイクルアセスメント(LCA)」は、商品設計や商品開発の意思決定するための指針にもなるのです。
製品のライフサイクル全体を考慮することは、『過剰包装』に対処する上で、具体的な対策を見つけ出すことができます。
持続可能な素材や製造方法の採用、エネルギー効率の向上、リサイクルの促進などの取り組みを通じて、環境に配慮したものに変えていくことが重要です。
日本の環境政策!法律があるにも関わらず進まない現状
日本には、環境にやさしい商品を選択する『グリーン購入法』や、プラスチックや紙製品などを分別しリサイクルする『容器包装リサイクル法』、社会や環境、製造過程を考慮して選択する『エシカル消費』があります。
このような環境に配慮した法律や政策が存在する一方、それらが十分に実行されず、環境保護の面での進歩が遅れているという問題があります。
具体的には、以下のような要因が挙げられます。
- 消費者の意識と行動
環境に配慮した商品を選ぶ人はいますが、まだまだ少数派。多くの人が価格や利便性を優先している。
- 法律の厳格さと執行不足
法律はあるけれども、その適用や罰則が弱い。企業や個人は法律を守る必要性を感じにくい状況。
- 産業構造の影響
既存の企業や伝統的な産業が、環境保護の事業へと変化できない。新技術や研究などの取り組みを導入することが難しい。
- 政府の対応の遅れ
政府の環境政策は進んでいるとは言い難く、他の先進国に比べると遅れている。再生可能エネルギーや温室効果ガス削減などの目標や政策が不十分。
これらの要因が合わさり、環境保護のための法律や政策が進まず、日本の環境への取り組みが遅れているのです。
『過剰包装』は、私たちの日常生活に大きな影響を与えています。買って捨てるだけの包装は、環境に大きな負担をかけています。
日本の包装産業は伝統的に様々な包装技術を持ち、包装に対する文化的な価値を感じています。そのため、政府や企業は、過剰包装や、包装廃棄物の問題への十分な取り組みが見られません。
企業の利益や、変わることのできない政府が、長期的な視野を持ち、積極的に転換していくことを願うばかりです。
次回は、過剰包装問題へ積極的に取り組んでいる、EU(欧州)について、具体的な対策を含めて解説していきます。
(後編は以下から)
【参考文献】
- 再生可能エネルギー及び水素エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン「https://www.env.go.jp/earth/ondanka/lca/index.html」環境省(参照:2024-4-10)
- 容器包装リサイクル法とは「https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html」環境庁(参照:2024-3-29)
- グリーン購入法について 「https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html」環境庁(参照:2024-3-29)
- エシカル消費とは「https://www.ethical.caa.go.jp/ethical-consumption.html」消費者庁(参照:2024-3-29)