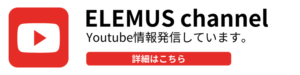最近では欧州での企業に求められる環境概念が活発化しています。
サスティナビリティ社会を目指し、EUが発足するCSRDでは、さまざまな環境視点での情報開示が求められています。
本記事では、CSRDにおける欧州の新基準、概念や日本企業に求められる対応について解説します。
欧州の新基準「CSRD」とは?

CSRDとは、EUより2023年1月に発行された「企業サステナビリティ報告指令」を意味します。
この報告指令とは、EU域内でのサスティナブルに関する情報開示の強化を目的とした新たな法律のことです。
開示すべき企業情報はおもにE : 環境、S : 社会、G : ガバナンスの項目に分かれ、株主・投資家などステークスホルダーが企業に対し持続可能性の視点からの判断を行えるよう支援します。
CSRDの開始時期について
CSRDは2023年1月に発行されたため、会計年度として2024年からが報告の対象期間となります。
対象となる企業は2025年の情報開示に備え、24年度からの対策が必要となるため、世界的に関心が高まっています。
また、CSRDと併せて確認すべき以下のワードも押さえておきましょう。
- ESRS
CSRDで開示、報告する情報の基準を示したもので、企業同士で比較、検討できるため報告内容に信頼性を高めることに繋がります。
- NFRD
2014年に導入された、CSRDと同様企業のサスティナビリティに関する情報開示を求める法律です。
CSRD発行前に欧州の大企業を対象とした規制として適用されて来ました。
NFRDの問題点
NFRDは従業員500人以上の大企業に対し環境・社会・従業員員・人権・汚職・贈収賄などの非財務情報を開示するよう働きかけるものでしたが、開示基準や適用範囲が明確でないこともあり、開示情報の質に企業ごとのばらつきが生じていました。
このためNFRDの問題点、改善すべきポイントを解決するため、新たにCSRDが発足されました。
CSRDでの新たな変更点について

NFRDからCSRDでの新たな変更点は以下の内容になります。
- 対象企業の拡大
従来のNFRDでは対象となる企業が限られていましたが、CSRDでは欧州に子会社のある企業なども、基準に該当していれば2024年度から適用となり、段階的に拡大されます。
- 第三者による保証の義務化
開示する情報について、NFRDでは第三者の保証は明記されていませんでした。
しかしCSRDでは情報の信頼性を高める目的で第三者による保証が新たに義務化されます。
CSRDの開示・報告内容とは?
CSRDの対象企業に必要な開示・報告内容は、「環境・社会・人権・ガバナンス」に関しての情報を含めた企業のサスティナビリティ関連の事柄です。
また、詳細な開示内容、項目は先ほどご紹介しましたESRS(欧州サステナビリティ報告基準)により定められています。
- ESRSの設定項目
ESRSの具体的な設定項目は、「ビジネスモデルと戦略・ESGリスク管理・ESG機会・ESG目標・ESG指標・ESGデータ・ESG報告の品質と併せて、先ほどの第三者保証に関する情報提供が義務付けされています。
- 情報開示の形式
開示する情報は、年次報告書として提出する「マネジメントレポート」内に記載することが義務付けされています。
また、提出時は財務情報・非財務情報をXHTML形式の単一フォーマットで提出する必要があります。
このようにCSRDでは開示情報を明確化・統一化が進み、サステナビリティ情報がより信頼性の高いものに変化しています。
また、企業間での比較性も向上しているため、より正確な情報収集が可能になっていると言えるでしょう。
情報開示のポイントとなる概念
ESRSでの情報開示では、ポイントとなる概念がありますのでご紹介します。
- ダブルマテリアリティ
ダブルマテリアリティの概念は、企業が率先して取組むべき「重要な課題」を意味します。
また、この重要な課題は、2つの側面を持ちます。
[財務的マテリアリティ]
環境・社会が企業に与える財務的な影響を指します。
[環境・社会的マテリアリティ]
企業が環境・社会に与える社会的な影響を意味します。
この概念に対し「シングルマテリアリティ」では企業が環境・社会から企業が受ける財務的な影響のみを考慮することを指します。
このシングルマテリアリティの概念は、TCFDなどのフレームワークで活用されていますので、それぞれの概念の違いに注意しましょう。
日本企業に課せられた課題は?
現在情報開示の業務で中心となっているTCFDなど、サステナビリティに先進的に取組む企業であっても、CSRDへの対応には新たな課題に取り組む必要があります。
具体的に想定される課題は以下の内容となります。
- ESRS基準への対応
ESRS基準で設定されている12のカテゴリーでは、例えば従来はE : 環境のみ対応していた企業であっても、新たに該当する場合、開示するための膨大な準備期間が発生します。
- 今後更なる課題も
今回2024年度にCSRDの開示対象となるのは、欧州の子会社のみと限定的ですが2028年に連結開示が開始される見通しとなり、連結後は過去データも開示する必要が出て来る可能性が高くなります。
このため、現段階からデータ収集や開示情報の策定を開始することが大切です。
まとめ
今回は、CSRDにおける欧州の新基準、概念や日本企業に求められる対応について解説しました。
企業のサスティナビリティに関する情報開示が求められるCSRDの基準、概念をお伝えしました。
国内の企業は、今後のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に対応可能な体制作りが急務です。
例えば社内のマネジメント管理を共通のプラットフォームで管理可能なERP、コンサルティングを導入するなどCSRDに耐えうる組織変革を実践して行きましょう。
【参考文献】
CSRDとは? 欧州のESG最新動向と、日本企業への影響や必要な対応を解説「https://www.asahi.com/sdgs/article/15208058」(参照)
CSRDとは!?概要・開示項目から日本企業におよぼす影響を解説「https://earthene.com/media/1567」(参照)